広告

「給湯器から異音が聞こえる」と不安を感じる方は多くいます。給湯器は毎日の生活に欠かせない設備です。この記事では、給湯器が壊れる前の兆候や対処法、寿命や交換のタイミングについて詳しく解説します。
記事を読めば、給湯器の故障を早期に発見し、適切な対応が可能になります。安全で快適な生活を送るための具体的な方法を身に付けましょう。
給湯器が壊れる前の代表的な兆候5選

給湯器が壊れる前の前兆は以下のとおりです。
- 本体からの水漏れ
- 異音(ピー音・ボンッという爆発音)や異臭(焦げ臭い・ガス臭い)
- お湯の温度が安定しない・ぬるい
- 追い炊きや点火がうまくいかない
- リモコンに頻繁にエラーコードが表示される
本体からの水漏れ

給湯器からの水漏れは、内部部品の劣化や配管の破損など、さまざまな原因で発生します。冬場は、配管内の水が凍結して膨張し、配管の破損を引き起こすリスクが高まります。パッキンの劣化や、ナットの緩みによる接続部からの漏水も多いので注意が必要です。
床や壁に湿りや水染みが確認された場合、給湯器内部からの漏水が進行している可能性があります。水漏れを放置すると、着火部分が常に湿った状態となり、点火不良や不完全燃焼を引き起こします。他の部品にも悪影響です。給湯器全体の故障にもつながります。
水漏れを発見したら、リモコンで給湯器の電源を切り、漏水箇所を確認しましょう。水圧の低下や給湯温度の不安定さなども、水漏れのサインとして注意が必要です。早期発見と迅速な対応が大きなトラブルを防ぎます。
» 給湯器の水漏れの原因と修理方法を徹底解説
» 寒さの厳しい冬も安心!給湯器の凍結を防ぐ方法と応急処置
異音(ピー音・ボンッという爆発音)や異臭(焦げ臭い・ガス臭い)

給湯器からの異常な音や異臭は、重大な故障のサインです。異音や異臭が発生する主な原因は以下のとおりです。
- 内部部品の摩耗による異音
- 燃焼不良による異臭
- ガス漏れの可能性
- 電気系統の不具合
- 設置環境の問題
異音や異臭が発生した場合、早急に専門家による点検を受けてください。爆発音のような大きな音や、焦げ臭いにおいを感じた場合は、直ちに使用を中止し、ガス栓を閉めましょう。設置環境の問題で異音や異臭が発生することもあるため、通風状態や周囲の状況も合わせて確認が必要です。
お湯の温度が安定しない・ぬるい

お湯の温度が安定しない現象は、給湯器の重大な不具合を示すサインです。温度が急に冷たくなったり熱くなったりしたら、内部の温度調整センサーの故障が考えられます。長時間使用した際に温度変化が目立つ場合、給湯器の機能低下が進行しています。
シャワーや入浴時の急激な温度変化は、火傷のリスクもあるため、早急な対応が必要です。サンドイッチ現象と呼ばれる「熱いお湯・冷たい水・熱いお湯」が交互に出る症状も、温度が不安定になるサインです。
水圧の変化や複数箇所での同時使用によって発生する場合もありますが、給湯器の経年劣化による可能性も考えられます。設定温度と実際の温度が大きく異なり、リモコンにエラーコードが表示されるなどがあれば温度調節ユニットの故障を疑いましょう。
» 給湯器のお湯が出ないときの原因と対処法を解説
追い炊きや点火がうまくいかない
給湯器の点火不良は、快適な生活に大きな支障をきたします。点火装置の不具合は、単なる不便さだけでなく、ガス漏れや不完全燃焼などの危険につながります。点火に関する問題は小さな異常から始まり、徐々に深刻化するため、早期発見と対応が重要です。点火がうまくいかない原因は以下のとおりです。
- 点火プラグの劣化
- ガス供給の問題
- 電源の不具合
- 点火装置の故障
- ガスバルブの異常
点火に関する問題は、複数の要因が絡み合って発生することが多いため、原因の特定には専門業者に相談しましょう。定期的な点検により、点火装置の劣化を早期に発見し、適切な対応が重要です。
リモコンに頻繁にエラーコードが表示される

給湯器に表示されるエラーコードは、機器の状態を正確に診断するための重要な情報です。各メーカーによって異なるコードが設定されており、具体的な不具合の内容と対処方法を示しています。代表的なエラーコードは以下のとおりです。
- 点火不良を示す「111」
- 温度ヒューズ断線を示す「140」
- 異常高温を示す「200」
- お湯の循環不足を示す「632」
- 水量サーボ異常を示す「661」
エラーコードが表示された場合、ユーザーマニュアルやメーカーのウェブサイトで対処方法を確認しましょう。一部のエラーはリセット操作で解決できますが、専門的な知識や技術が必要な場合も多くあります。複数の異なるエラーコードが頻繁に表示されるなら、給湯器の深刻な故障が疑われます。
エラーコードは給湯器からの重要なメッセージとして、適切な対応が重要です。
その症状は危険?今すぐ使用を中止すべき「緊急度」の判定基準

異変を感じた際、それが「今すぐ止めるべきもの」か「様子を見て良いもの」かを判断する基準を知っておきましょう。
- 【危険度:高】直ちにガス栓を閉めて業者を呼ぶべきケース
- 【危険度:中】早めの点検・修理を検討すべきケース
- 【注意】故障ではないかも?冬場に多い「お湯が出ない」原因と対策
【危険度:高】直ちにガス栓を閉めて業者を呼ぶべきケース
以下の症状がある場合は、爆発や一酸化炭素中毒、火災の恐れがあるため即座に使用を中止してください。
- ガス臭い、または焦げ臭い匂いが漂っている
- 点火時に激しい爆発音(ボンッ)がする
- 給湯器本体から黒い煙が出ている
- 排気口周りが煤(すす)で黒くなっている
これらの症状は、ガス漏れや不完全燃焼が起きている明らかな証拠です。電源を切るだけでなく、建物の外にあるガスの元栓を閉め、火気を一切近づけないようにしてください。夜間や休日であっても、ガス会社の緊急窓口や24時間対応の修理業者へ連絡し、安全が確認されるまで給湯器には触れないのが鉄則です。
【危険度:中】早めの点検・修理を検討すべきケース
すぐに危険ではないものの、近いうちに完全に故障する可能性が高い症状です。
- お湯の温度が頻繁に変動する
- 本体から常に水が漏れている
- エラーコードが週に何度も出る
- 以前よりも稼働音が大きくなった
水漏れや異音は、時間が経過して自然に治ることはありません。むしろ徐々に悪化し、他の正常な部品まで故障させてしまう二次被害を招きます。お湯が使えるからといって騙しだまし使うと、最もお湯を必要とする極寒の日などに突然壊れて大変な思いをすることになります。平日の日中など、時間に余裕があるうちに点検を依頼しましょう。
【注意】故障ではないかも?冬場に多い「お湯が出ない」原因と対策
故障と間違えやすいのが、冬場特有の「凍結」や「一時的な過負荷」によるトラブルです。氷点下になる夜に配管内の水が凍ると、給湯器が正常でもお湯が出なくなります。この場合、エラーコード「290」などが出ることもありますが、日が昇って気温が上がれば自然に解消されるため修理の必要はありません。
また、冬場は水温が低いため、設定温度にするために給湯器がフル稼働します。その結果、お湯の勢い(水圧)が弱くなることがありますが、これは一度に温められる水の量に限界があるためで、故障ではありません。焦って業者を呼ぶ前に、外気温の影響やガスメーターの遮断(マイコンメーターの復帰が必要な状態)を確認することで、無駄な出張費を支払わずに済みます。
給湯器の寿命と交換のタイミング

給湯器の交換は、使用年数や故障の状況を考慮した判断が重要です。給湯器の一般的な寿命や交換を検討するタイミングについて解説します。
給湯器の一般的な寿命
給湯器の一般的な寿命は約10年からと言われます。適切なメンテナンスをすると、最大で20年近くまで使用可能です。寿命は給湯器の種類や使用頻度、水質などの要因に影響を受けます。ガス給湯器は電気給湯器と比べて寿命が短い傾向にあり、硬水地域での使用は水中のカルシウム蓄積により寿命を縮めます。
寿命を延ばすには、定期的な点検や適切なメンテナンスが不可欠です。部品の交換や清掃を計画的に行って、給湯器の健全性を保ちましょう。使用年数が10年を超えた給湯器は、故障のリスクが高まるため、交換をおすすめします。
» 給湯器の寿命と交換時期の見極め方を詳しく解説
「修理」か「交換」か?迷った時の判断基準フロー
修理すべきか、新しいものに買い替えるべきかの判断は、以下のフローチャートを参考にしてください。
| 状況 | 推奨される対応 |
| 設置から5年未満 | 修理(メーカー保証や延長保証が使える可能性大) |
| 設置から7〜9年 | 故障箇所が軽微なら修理、重度なら交換を検討 |
| 設置から10年以上 | 交換を強く推奨(他箇所の故障リスクが高いため) |
5年以内であれば、一度修理すればその後も長く使える可能性が高いです。しかし、10年近く経過している場合、一箇所を修理してもすぐに別の箇所が壊れる「故障の連鎖」が起きるリスクがあります。何度も修理費を支払うよりも、最新の省エネ機種に交換して光熱費を抑える方が、トータルコストでは安くなるケースがほとんどです。
10年以上経過しているなら修理より交換がお得な理由
10年を超えた給湯器を修理することは、経済的なメリットが少ないと言わざるを得ません。古い機種は燃費が悪く、最新の「エコジョーズ」などと比較すると年間のガス代に大きな差が出ます。また、古い給湯器の修理代に数万円かけても、その数ヶ月後に本体の寿命で結局交換することになれば、修理代が全くの無駄になってしまいます。
最新機種は熱効率が飛躍的に向上しており、月々のガス代を約10〜15%削減できるモデルも珍しくありません。故障の不安を抱えながら使い続ける精神的なストレスや、突然お湯が出なくなるリスクを考えれば、10年という節目で一新するのが最も賢明な判断です。長期的な視点で見れば、故障前の交換が最もコストパフォーマンスに優れています。
交換を検討するべきタイミング
給湯器の交換を検討するタイミングは以下のとおりです。
- 使用開始から10年以上経過している
- 頻繁に修理をしている
- 最新の省エネ基準に適合しない機種である
- 修理後も故障が再発する
- 使用時のエネルギーコストが増加する
給湯器の修理費用は1〜5万円程度が一般的です。修理箇所によって費用は変動し、燃焼系統の故障は部品代が高額になりやすいため、交換を視野に入れましょう。補助金制度を利用すれば、高効率な給湯器に交換する費用が抑えられる可能性があります。
» 給湯器の交換はどこに頼む?各業者の特徴と選び方のポイント
給湯器に壊れる前兆があったときの対処法

給湯器に壊れる前兆があったときの対処法は、以下のとおりです。
- まずはリモコンのリセットと電源プラグの抜き差しを試す
- 賃貸物件の場合は大家・管理会社へ連絡
- 持ち家の場合は専門業者(メーカー・ガス会社・交換業者)へ相談
まずはリモコンのリセットと電源プラグの抜き差しを試す
軽微なシステムエラーであれば、リセット操作で復旧することがあります。まずは給湯器のリモコンで電源を切り、再度入れてみてください。それでも改善しない場合は、屋外にある給湯器本体のコンセントを一度抜き、数分待ってから差し直してみましょう。スマートフォンの再起動と同じ原理で、内部のプログラムが整理され、正常に戻る場合があります。
ただし、異音や異臭がある場合はこの操作を行ってはいけません。無理に再起動させようとすると、異常な燃焼を促して火災を招く恐れがあります。あくまで「お湯の出が悪い」「画面表示がおかしい」といった、安全上の懸念が少ない場合に限って試してください。リセットしてもエラーが消えない場合は、物理的な故障ですので専門家に任せましょう。
賃貸物件の場合は大家・管理会社へ連絡
アパートやマンションなどの賃貸物件にお住まいの場合、給湯器の所有権は大家さんにあります。勝手に修理業者を呼んだり交換したりすると、費用の自己負担を求められるだけでなく、退去時にトラブルになる可能性があります。まずは管理会社か大家さんに連絡し、症状を伝えて指示を仰ぐのが正しい手順です。
経年劣化による故障であれば、修理や交換の費用は大家さん側の負担となるのが一般的です。管理会社が提携している業者が迅速に対応してくれるケースも多いです。連絡する際は、給湯器の型番や表示されているエラーコードをメモしておくと、話がスムーズに進みます。自分で手配する前に、必ず契約内容を確認しましょう。
持ち家の場合は専門業者(メーカー・ガス会社・交換業者)へ相談
戸建てや分譲マンションの所有者は、自分で業者を選んで依頼する必要があります。相談先は大きく分けて「メーカー」「ガス会社」「給湯器交換専門店」の3つです。保証期間内であればメーカーが確実ですが、交換を安く済ませたいのであれば、流通コストを抑えている交換専門店が最も費用を抑えられる傾向にあります。
地元のガス会社は安心感がありますが、価格は定価に近く高めになることが多いです。緊急時であれば、24時間対応可能で最短即日交換を謳っているネット系の交換業者に見積もりを依頼するのが効率的です。複数の業者から見積もりを取り、価格だけでなく保証内容や口コミを比較して、信頼できるパートナーを選びましょう。»水まわりのトラブルとは?対処法と業者選びのポイントを解説
給湯器の修理・交換費用の相場

給湯器が故障した際に気になるのが修理や交換にかかる費用です。ここからは、修理費用の目安や交換費用を抑えるコツ、さらに補助金や助成金を活用する方法を紹介します。
- 修理費用の目安と確認すべきポイント
- 本体交換費用の相場と費用を抑えるコツ
- 知らなきゃ損!自治体の補助金や省エネ助成金を活用する方法
修理費用の目安と確認すべきポイント
給湯器の修理費用は故障の部位や程度によって大きく異なります。比較的軽微な故障なら数千円〜2万円程度で済むケースもありますが、主要部品の交換が必要な場合は3万円以上かかることも珍しくありません。修理を依頼する前に確認すべきポイントは、給湯器の使用年数です。一般的に給湯器の耐用年数は8〜10年程度とされており、それを超えている場合は修理よりも交換を検討した方が経済的な場合があります。
以下は代表的な故障と修理費用の目安です。
| 故障内容 | 修理費用相場 | 交換部品 |
| 点火しない | 5,000円〜20,000円 | 点火装置、電極 |
| お湯の温度が安定しない | 10,000円〜30,000円 | 混合弁、サーミスタ |
| 水漏れがする | 15,000円〜40,000円 | パッキン、熱交換器 |
| エラーコード表示 | 8,000円〜50,000円 | 基板、センサー類 |
修理費用が給湯器本体価格の50%を超える場合は、本体交換を検討するのが一般的です。また、重要部品(熱交換器など)の故障は高額修理になりやすく、耐用年数が近い場合は交換がおすすめです。修理業者を選ぶ際は、複数社から見積もりを取ることと、出張費や診断料の有無を事前に確認することが重要です。透明性の高い料金体系を提示している業者を選びましょう。
本体交換費用の相場と費用を抑えるコツ

給湯器の本体交換費用は、機種や取付工事の難易度によって変わります。一般的な相場としては、本体価格と工事費を合わせて以下のようになります。
| 給湯器の種類 | 交換費用相場(税込) |
| ガス給湯器(従来型) | 8万円〜15万円 |
| エコジョーズ | 15万円〜25万円 |
| 電気温水器 | 15万円〜30万円 |
| エコキュート | 35万円〜60万円 |
| 石油給湯器 | 10万円〜20万円 |
交換費用を抑えるコツとしては、次のポイントがあります。
- オフシーズン(夏場など)に交換を計画する
- 複数業者から見積もりを取る
- メーカーキャンペーンや期間限定特価を活用する
- 補助金・助成金を利用する
- 現在の設置場所や配管をそのまま利用できる機種を選ぶ
特に工事費を抑えるには、現状の設置環境を大きく変えない機種選びが重要です。配管の引き直しや電気工事が必要になると、工事費が大幅に増加します。また、インターネット通販で給湯器を購入し、工事のみ業者に依頼する方法もありますが、保証やアフターサービスの面でリスクがあることも覚えておきましょう。
知らなきゃ損!自治体の補助金や省エネ助成金を活用する方法
環境に配慮した高効率給湯器への交換を後押しするため、国や自治体による補助金・助成金制度があります。これらを利用することで、導入コストを大幅に抑えることができます。
国の補助金制度としては、「住宅省エネ2025キャンペーン」などがあり、一定の条件を満たすと最大で数万円の補助が受けられます。特にエコキュートやエコジョーズなどの省エネ性能の高い給湯器が対象になることが多いです。また、自治体独自の助成制度も多く存在します。以下は補助金を受けるための一般的な条件です。
- 一定の省エネ性能を満たす製品であること
- 住宅の所有者または居住者であること
- 新築ではなくリフォームや機器交換であること
- 指定工事業者による施工であること
補助金の申請には事前申請が必要な場合と工事後の申請が可能な場合があります。申請期限や必要書類も異なるため、工事を検討する際には早めに自治体のホームページなどで確認しておくことをおすすめします。
利用可能な補助金・助成金の例
| 制度名 | 対象機器 |
| 住宅省エネ2025キャンペーン | 高効率給湯器 |
| 東京都地球温暖化対策報奨金 | エコキュート、など |
| 各自治体独自の助成金 | 自治体により異なる |
補助金・助成金は予算に限りがあるため、申請が多い場合は早期に終了することがあります。検討中の場合は早めに申請することをおすすめします。
給湯器の交換業者の選び方

給湯器の交換業者を選ぶ際の重要なポイントは以下のとおりです。
- 必要な資格を保有しているか
- 口コミや施工実績が豊富で透明性があるか
- 保証内容とアフターサービス(24時間対応など)の充実度
上記のポイントを総合的に確認し、安全かつ信頼できる業者を選択しましょう。
必要な資格を保有しているか
給湯器の交換や修理を行う業者選びでは、適切な資格の有無が最も重要な判断基準です。ガス給湯器の取り扱いには「高圧ガス取扱者」の資格が必須になります。高圧ガス取扱者は、ガス機器の安全な取り扱いと設置に関する専門的な知識と技術を証明するものです。
業者が所属する団体や登録制度への加入状況も、信頼性を判断する重要な要素になります。業界団体への加入は、安全基準や品質基準の遵守を示す指標です。施工に関する正式なライセンスや認可の確認も不可欠で、業者の技術力と安全管理能力を保証します。
国家資格を持つ技術者の在籍は、より高度な技と知識を持った対応が期待できます。資格の有無は、工事の品質だけでなく、事故防止や保険適用の面でも重要です。資格情報は必ず事前に確認し、適切な資格を持つ業者を選択しましょう。安全で確実な工事を進めてもらえます。
口コミや施工実績が豊富で透明性があるか
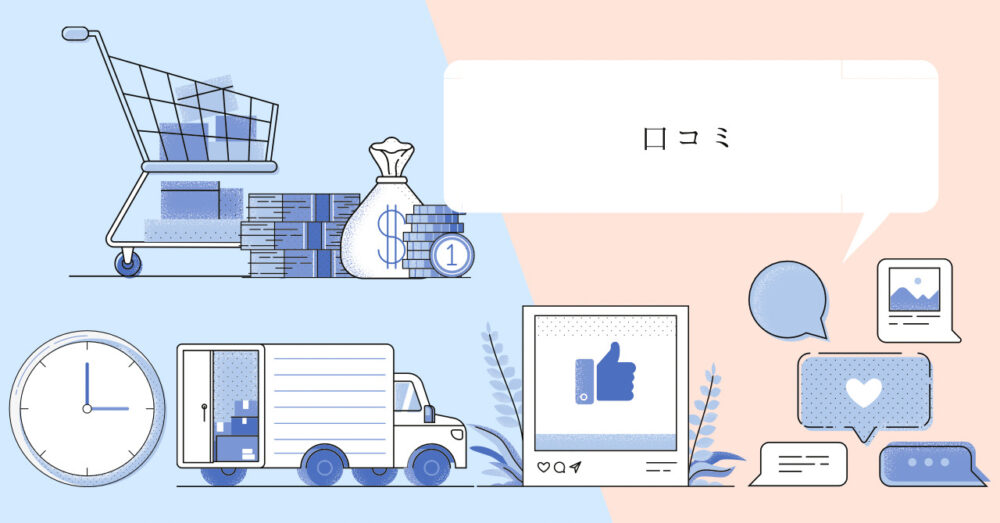
給湯器の交換業者を選ぶ際は、口コミや評判もチェックしましょう。実際の施工事例や顧客の評価を確認すると、業者の技術力や対応の質を客観的に判断できます。地域密着型の業者の場合、地域での評判は信頼性の高い指標です。信頼できる業者の特徴は以下のとおりです。
- 迅速で丁寧な対応力
- 優れた費用対効果
- 充実したアフターサービス
- 高い技術力と安全性
- 透明性の高い情報開示
良質な業者は、施工事例や価格体系を明確に開示し、顧客からの評価も積極的に公開しています。過度に安価な見積もりや、不明確な料金体系を提示する業者には注意が必要です。実績豊富で、地域での信頼度が高い業者を選ぶと、安心して工事を依頼できます。
» 水道業者ぼったくりの対処法
保証内容とアフターサービス(24時間対応など)の充実度
給湯器のアフターサービスは、長期的な安全性と性能維持の要となる重要な要素です。優れたアフターサービスを提供する業者は、突発的な故障や不具合に対して迅速な対応が可能です。定期的な点検やメンテナンスにより、問題の早期発見と予防的な対応が実現できます。
アフターサービスの質は、給湯器の寿命と使用時の安全性に直接影響するため、業者選定の際の重要な判断基準です。注目する点は、保証期間の長さや対応範囲、24時間サポート体制の有無、定期点検の内容と頻度です。契約前に具体的なサービス内容を確認し、必要なサポートが受けられるか慎重に検討しましょう。
給湯器の定期点検とメンテナンス

給湯器を安全で長く使い続けるためには、定期的な点検と日常的なメンテナンスが重要です。ここでは、専門業者による点検の適切なタイミングや、自分で簡単にできるセルフチェックの方法、メンテナンス記録を残すことの大切さを紹介します。
- 排気口・吸気口周りに物を置かない
- 浴槽フィルターの清掃と水抜き栓の点検
- 専門業者に依頼する点検のタイミング
- メンテナンス記録(点検日・内容)を保管するメリット
排気口・吸気口周りに物を置かない
給湯器を長持ちさせるための最も簡単な方法は、周囲の環境を整えることです。特に排気口や吸気口の周りに物置やゴミ箱、植木鉢などを置いてはいけません。空気の流れが遮られると、給湯器が正常に酸素を取り込めなくなり、不完全燃焼の原因となります。これは内部に煤を溜め、部品の劣化を急激に早める致命的な要因です。
排気が滞ると、排出された熱風を再び吸い込んでしまう「ショートサイクル」という現象が起き、本体温度が異常に上昇します。これが安全装置の作動や故障を招きます。給湯器の周囲60cm以内には物を置かないスペースを確保し、常に風通しの良い状態を保つよう意識してください。これだけで故障率はぐっと下がります。
浴槽フィルターの清掃と水抜き栓の点検
追い炊き機能付きの給湯器をお使いの場合、浴槽内の循環アダプターにあるフィルターの清掃が欠かせません。フィルターに髪の毛や湯垢が詰まると、お湯の循環が悪くなり、ポンプに過度な負担がかかります。これが「追い炊きができない」「温度が上がらない」といった故障の原因となります。週に一度は取り外して、歯ブラシなどで汚れを落としましょう。
給湯器下部にある「水抜き栓」周辺の点検も有効です。ここにはストレーナーというゴミ受けが内蔵されているモデルもあり、配管からのサビや砂が溜まると水圧低下を招きます。自分で操作するのが不安な場合は、年に一度の定期点検を業者に依頼する際、一緒に清掃してもらうのがおすすめです。小さなゴミを取り除くだけで、大きな故障を未然に防げます。
専門業者に依頼する点検のタイミング
給湯器の安全性と効率を維持するためには、専門業者による定期点検が重要です。一般的に推奨される点検のタイミングは1〜2年に1回程度です。特に以下のような場合は、定期点検を検討する良いタイミングです。
- 購入から3年以上経過している
- 使用頻度が特に高い
- 異音や異臭などの異常を感じる
- 長期間使用していなかった後の再使用時
- 引っ越し後の初使用前
プロの点検では、燃焼状態や安全装置の確認、配管接続部の漏れチェック、電気系統の点検など、専門的な観点から給湯器の状態を評価します。
| 点検内容 | 確認ポイント | 目的 |
| 燃焼状態の確認 | 火の色、異音、異臭 | 不完全燃焼防止 |
| 安全装置のチェック | 各種センサー、遮断弁 | 事故防止 |
| 配管接続部の点検 | 水漏れ、ガス漏れ | 漏洩事故防止 |
| 電気系統の点検 | 接続部、制御基板 | 電気系統の故障防止 |
| 熱交換器の状態確認 | 詰まり、腐食 | 熱効率の維持 |
専門業者による点検費用は、5,000円〜15,000円程度が相場です。メーカーの有償点検サービスを利用する方法もあります。定期点検はコストがかかりますが、故障を早期発見して大きな修理費用を未然に防ぐことができるため、長期的には経済的です。特に10年以上使用している古い給湯器は、安全面からも定期点検をおすすめします。
メンテナンス記録(点検日・内容)を保管するメリット
給湯器の点検や修理を行った際は、その内容を必ず記録して保管しておきましょう。いつ、どの部品を交換したかの履歴があると、次に不具合が起きた際に「別の箇所の寿命か、前回の修理ミスか」の判断が容易になります。プロの業者にとっても、過去のカルテがあることで故障診断の精度が上がり、無駄な調査時間を省くことができます。
記録があることで保証期間の管理も確実になります。「まだ保証内だと思っていたら数日過ぎていた」という悲劇を防げます。取扱説明書と一緒に、修理の明細書や保証書を一つのファイルにまとめておき、給湯器本体にも「次回の点検推奨時期」をメモして貼っておくのがおすすめです。計画的なメンテナンスが、結果として家計を守ることに繋がります。
給湯器に関するよくある質問

- 異音がするけれど、すぐに修理を依頼しないと危険ですか?
- 古い給湯器を交換するとき、撤去費用はどのくらいかかるのでしょうか?
- 高効率タイプの給湯器は本当にお得ですか?
異音がするけれど、すぐに修理を依頼しないと危険ですか?
給湯器から異音が聞こえた際は、音の種類や状況に応じて対応が異なります。
- 正常な運転音の場合
- 特に問題はありませんので、過剰な心配は不要です。
- 「ボンッ」という音がする場合
- 不完全燃焼やガス漏れのリスクがある可能性が高いため、直ちに使用を中止して専門業者に連絡してください。
- 購入から10年以上経過した給湯器の場合
- 異音が続く場合は、本体の劣化や故障が疑われます。業者に点検を依頼することをおすすめします。
異音は故障の初期症状であることが多いため、早めの点検が安心です。
古い給湯器を交換するとき、撤去費用はどのくらいかかるのでしょうか?

給湯器の撤去費用は、種類や業者によって変動します。以下に一般的な費用相場を示します。
- エコキュートの場合:撤去費用の相場は10,000〜20,000円程度です。
- 一般的なガス給湯器の場合:撤去処分費用の相場は約5,000円です。
具体的な費用は、給湯器の種類や設置状況、撤去作業の難易度によって変動します。事前に見積もりを依頼することをお勧めします。
高効率タイプの給湯器は本当にお得ですか?
高効率給湯器(エコジョーズやエコキュートなど)は、省エネルギー性能が高く、光熱費を削減できるため長期的に見て経済的です。
- エコジョーズ:従来型よりガス使用量を約15%削減可能。
- エコキュート:深夜電力を利用し、電気代を大幅に節約。
初期費用は高めですが、エネルギーコストの削減効果により、導入から数年で元が取れるケースもあります。
まとめ

給湯器は、日常生活に欠かせない重要な設備です。水漏れや異音、温度の不安定さなど、故障の前兆に早めに気付けば、大きなトラブルを防げます。寿命や使用状況を考慮し、計画的な交換を検討することも重要です。信頼できる業者を選び、適切な時期に交換すると、より効率的で安全な給湯設備の運用が可能になります。
必要に応じて専門家に相談するのも有効です。定期的なメンテナンスと適切な使用方法を心がけ、安全に給湯器を使用しましょう。